|
1.大海人皇子
(おおあまのみこ)
=天武天皇
(てんむてんのう)
天智天皇の弟。兄天智天皇の近江朝に皇太子であったが吉野で出家する。天智天皇の死後、壬申の乱に勝利し、飛鳥浄御原宮で即位し天武天皇となる。改新事業を進めて天皇の権威を確立した。額田王をめぐる兄弟の確執が伝えられている。
|

|
代表歌
●紫草の にほへる妹を 憎くあらば 人妻ゆゑに われ恋ひめやも (1-21) ※
●よき人の よしとよく見て よしと言ひし 吉野よく見よ よき人よく見つ(1-27)
●わが里に 大雪降れり 大原の 古りにし里に ふらまくは後 (2-103)
 上記代表歌が、読み仮名付きでご覧いただけます。(PDF版)
上記代表歌が、読み仮名付きでご覧いただけます。(PDF版)
▲このページのTOPへ
|
|
2.大伴旅人
(おおとものたびと)
天智4年(665年)生まれ、天平3年(731年)没(67歳)。山上憶良と同時期に九州太宰府に赴任し、交流を重ねる。漢詩文の教養も深く、憶良とともに新しい傾向を示す。歌は人事を主とし、平明な優雅な歌風。赴任中に愛妻を亡くし、さびしい老境を送った。その憂いを酒によってまぎらしたか、酒を讃むる歌が13首収められている。
|

|
代表歌
●浅茅原つばらつばらに もの思へば 故りにし郷し 思ほゆるかも(3-333)
●験なき ものを思はずは 一杯の 濁れる酒を 飲むべくあるらし(3-338)
●なかなかに 人とあらずは 酒壺に なりにてしかも 酒に染みなむ(3-343)
●あな醜く 賢しらをすと 酒飲まぬ 人をよく見ば 猿にかも似む(3-344)
●この世にし 楽しくあらば 来む世には 虫に鳥にも われはなりなむ (3-348) ※
●人もなき むなしき家は 草枕 旅にまさりて 苦しかりけり(3-451)
●妹として 二人作りし わが山斎は 木高く繁く なりにけるかも (3-452) ※
●世の中は 空しきものと 知る時し いよよますます 悲しかりけり(5-793)
 上記代表歌が、読み仮名付きでご覧いただけます。(PDF版)
上記代表歌が、読み仮名付きでご覧いただけます。(PDF版)
▲このページのTOPへ
|
|
3.大伴家持
(おおとものやかもち)
第四期の歌人、大伴旅人の長男。各地の地方官を歴任した。叔母の大伴坂上郎女に育てられたことで文学的環境にも恵まれて文才を伸ばした。万葉集の編者といわれ、長歌46首、短歌426首、旋頭歌1首が収められている。日記のような形で歌を残している。万葉集最後の歌は因幡守で44歳の時作られたもの。すぐれた歌の数々は後の作品に大きな影響を与えている。
|
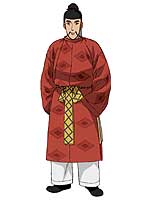
|
代表歌
●夢の逢は 苦しかりけり 覚きて かき探れども 手にも触れねば(4-741)
●春の苑 紅にほふ 桃の花 下で照る道に 出で立つ をとめ (19-4139) ※
●わが苑の すももの花か 庭に散る はだれのいまだ 残りたるかも(19-4140)
●春の野に 霞たなびき うらがなし この夕かげに 鶯鳴くも(19-4290)
●我が屋戸の いささ群竹 吹く風の 音のかそけき この夕べかも (19-4291) ※
●うらうらに 照れる春日に 雲雀あがり 心悲しも 独りし思へば(19-4292)
●移り行く 時見るごとに 心いたく 昔の人し 思ほゆるかも(20-4483)
●新しき 年の始めの 初春の 今日降る雪の いや重け吉事 (20-4516) ※
 上記代表歌が、読み仮名付きでご覧いただけます。(PDF版)
上記代表歌が、読み仮名付きでご覧いただけます。(PDF版)
▲このページのTOPへ
|
|
4.小野老
(おののおゆ)
第三期の歌人で、大宰の少弐として大伴旅人の下にあった。万葉集には短歌三首を残している。
|
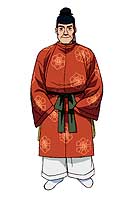
|
代表歌
●あをによし 奈良のみやこは 咲く花の にほふがごとく 今盛りなり (3-328) ※
●梅の花 今咲けるごと 散り過ぎず 我が家の苑に ありこせぬかも (5-816)
●時つ風 吹くべくなりぬ 香椎潟 潮干の浦に 玉藻刈りてな (6-958)
 上記代表歌が、読み仮名付きでご覧いただけます。(PDF版)
上記代表歌が、読み仮名付きでご覧いただけます。(PDF版)
▲このページのTOPへ
|
|
5.柿本人麻呂
(かきのもとのひとまろ)
天皇を称える歌を詠んだり、皇子たちに歌を捧げたりする宮廷歌人で、持統・文武両天皇を中心とする藤原京の全盛期に活躍。叙情歌人として、長歌・短歌・旋頭歌のいずれにもすぐれていた。万葉集に長歌19首、短歌75首が収められ、格調高い歌風で万葉集第一の歌人といわれ、後世、『歌聖』と呼ばれた。しかし、その生涯は謎に包まれている。
|
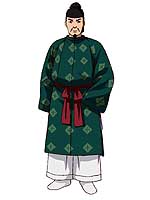
|
代表歌
●見れど飽かぬ 吉野の川の 常なめの 絶ゆることなく また還り見む(1-37)
●阿騎の野に 宿る旅人 うちなびき 寐も寝らめやも いにしへ思ふに(1-46)
●まくさかる 荒野にはあれど もみぢ葉の 過ぎにし君が 形見とぞこ来し(1-47)
●東の 野に炎の 立つ見えて かへり見すれば 月傾きぬ (1-48) ※
●日並知の 皇子の尊の 馬並めて 御猟立たしし 時は来向ふ(1-49)
●天さかる ひなの長道ゆ 恋ひ来れば 明石の門より 大和島みゆ(3-255)
●淡海の海 夕波千鳥 汝が鳴けば 心もしのに 古昔思ほゆ(3-266)
●ひさかたの 天の香具山 この夕べ 霞たなびく 春立つらしも(10-1812)
 上記代表歌が、読み仮名付きでご覧いただけます。(PDF版)
上記代表歌が、読み仮名付きでご覧いただけます。(PDF版)
▲このページのTOPへ
|
|
6.持統天皇
(じとうてんのう)
第二期の歌人。天智天皇の皇女。天武天皇の皇后となり、天皇崩御後あとをうけて即位された。後に都を藤原の宮へ移す。
|

|
代表歌
●春過ぎて 夏来るらし 白栲の 衣乾したり 天の香具山 (1-28) ※
●燃ゆる火も 取りてつつみて 袋には 入ると言はずやも 知るといはなくも(2-160)
●北山に つらなる雲の 青雲の 星離りゆき 月も離りて(2-161)
 上記代表歌が、読み仮名付きでご覧いただけます。(PDF版)
上記代表歌が、読み仮名付きでご覧いただけます。(PDF版)
▲このページのTOPへ
|
|
7.天智天皇
(てんじてんのう)
=中大兄皇子
(なかのおおえのおうじ)
第一期の歌人。舒明天皇の皇子で中大兄皇子と称したころ、中臣鎌足とともに蘇我氏を滅ぼし、大化の改新をおこなった。即位後、近江大津宮に都を移した。弟の大海人皇子と額田王をめぐって確執があったと伝えられる。
|

|
代表歌
●香具山と 耳梨山と あひし時 立ちて見に来し 印南国原(1-14)
●わたつみの 豊旗ぐも雲に 入日さし 今夜の月夜 あきらけくこそ(1-15)
●妹が家も つぎて見ましを 大和なる 大島の嶺に 家もあらましを(1-91)
 上記代表歌が、読み仮名付きでご覧いただけます。(PDF版)
上記代表歌が、読み仮名付きでご覧いただけます。(PDF版)
▲このページのTOPへ
|
|
8.額田王
(ぬかたのおおきみ)
女性であってもきわだった存在のためか、額田女王と書かなくても額田王と書き、ぬかたのおおきみと称している。第一期の代表的歌人で巫女のような役目をもって宮廷に仕えていた。大海人皇子(後の天武天皇)の妃となって十市皇女を産む。しかし、のちに大海人皇子の兄の天智天皇に召されて大津の宮に入る。歌と恋に生きた万葉集を代表する女流歌人で、叙景歌・叙情歌の両方に優れていた。
|

|
代表歌
●秋の野の み草刈り葺き 宿れりし 宇治の宮処の 仮廬し思ほゆ(1-7)
●熟田津に 船乗りせむと 月待てば 潮もかなひぬ 今はこぎ出でな (1-8) ※
●うま酒 三輪の山 あをによし 奈良の山の 山の際に い隠るまで 道の隈 い積るまでに つばらにも 見つつ行かむを しばしばも 見さけむ山を 心なく 雲の 隠さふべしや(1-17)
反歌
三輪山を しかも隠すか 雲だにも 心あらなむ 隠さふべしや(1-18)
●あかねさす 紫野行き 標野行き 野守は見ずや 君が袖振る (1-20) ※
●古に 恋ふらむ鳥は ほととぎす けだしや鳴きし 吾が思へるごと(2-112)
●君待つと 吾が恋ひをれば 我が屋戸の すだれ動かし 秋の風吹く (4-488) ※
 上記代表歌が、読み仮名付きでご覧いただけます。(PDF版)
上記代表歌が、読み仮名付きでご覧いただけます。(PDF版)
▲このページのTOPへ
|
|
9.山上憶良
(やまのうえのおくら)
第三期の代表歌人。遣唐使の書記官として唐に渡る。帰朝後地方官を歴任し、晩年の筑前守在任中に大伴旅人等と親交を重ねる。豊かな学識を持ち、現実的な人生問題や社会問題を読み、万葉集には有名な貧窮問答歌をはじめ79首の歌が収められている。
|

|
代表歌
●憶良らは 今は罷らむ 子泣くらむ それその母も 吾を待つらむぞ(3-337)
●瓜食めば 子ども思ほゆ 栗食めば ましてしのはゆ いづくより 来たりしものぞ まなかひに もとなかかりて 安眠し寐さぬ(5-802)
反歌
銀も 金も玉も 何せむに 勝れる宝 子に及かめやも(5-803) ※
●天ざかる 鄙に五年 住まひつつ 京の風俗 忘らえにけり(5-880)
●世の中を 憂しとやさしと 思へども 飛び立ちかねつ 鳥にしあらねば(5-893)
●士やも 空しかるべき 万代に 語りつぐべき 名は立てずして(6-978)
 上記代表歌が、読み仮名付きでご覧いただけます。(PDF版)
上記代表歌が、読み仮名付きでご覧いただけます。(PDF版)
▲このページのTOPへ
|
|
10.防人歌
(さきもりのうた)
防人とは九州の要所を防備するために派遣された兵士のことで、白村江の戦いでの大敗後、対馬・壱岐・筑紫におかれたはじめたと伝えられる。もっぱら東国の男たちが狩り出された。三年間勤めると交替した。防人の歌は純情素朴で方言などもそのまま用いられ、汲めども尽きぬ人間味が示されており、読む人の心を打つ。これらの歌が収録されていることは、万葉集の価値を高めている。
|

|
代表歌
●わが妻は いたく恋ひらし 飲む水に 影さへ見えて 世に忘られず(20-4322)
●時時の 花は咲けども 何すれぞ 母とふ花の 咲き出来ずけむ(20-4323)
●忘らむと 野行き山行き 我来れど わが父母は 忘れせぬかも(20-4344)
●父母が 頭かきな撫で 幸くあれて いひし言葉ぜ 忘れかねつる (20-4346) ※
●韓衣 裾に取りつき 泣く子らを 置きてそ来ぬや 母なしにして (20-4401) ※
●日な雲り 碓氷の坂を 越えしだに 妹が恋ひしく 忘らえぬかも(20-4407)
●防人に 行くは誰が夫と 問ふ人を 見るが羨しさ 物思もせず(20-4425)
 上記代表歌が、読み仮名付きでご覧いただけます。(PDF版)
上記代表歌が、読み仮名付きでご覧いただけます。(PDF版)
▲このページのTOPへ
|
|
11.東歌
(あずまうた)
「東歌」とは遠江(静岡県)・信濃(長野県)から東北地方にかけて、東国の庶民の間に歌われた民謡風の歌を中心にしている。日々の生活や労働の様子が歌いこまれ、素朴な感情や東国の方言などが見られて興味深い。
|

|
代表歌
●夏麻引く 海上潟の 沖つ洲に 船はとどめむ さ夜更けにけり(14-3348)
●筑波嶺に 雪かも降らる 否をかも 愛しき児ろが 布乾さるかも(14-3351)
●多摩川に さらす手作り さらさらに 何そこの児の ここだ愛しき (14-3373) ※
●信濃路は 今の墾道 刈株に 足踏ましなむ 履はけわが背(14-3399)
●信濃なる 千曲の川の 細石も 君し踏みてば 玉と拾はむ(14-3400)
●稲つけば かかる吾が手を 今夜もか 殿の若子が 取りて嘆かむ(14-3459)
●烏とふ 大をそ鳥の まさでにも 来まさぬ君を ころくとぞ鳴く(14-3521)
 上記代表歌が、読み仮名付きでご覧いただけます。(PDF版)
上記代表歌が、読み仮名付きでご覧いただけます。(PDF版)
▲このページのTOPへ
|
![]()
![]() 株式会社サン・エデュケーショナル
TEL:03-5428-5675 / FAX:03-5428-5674
株式会社サン・エデュケーショナル
TEL:03-5428-5675 / FAX:03-5428-5674